5月から保育園に通い始めて2週間ごとに熱を出していて熱は治って保育園に通わせてたのですが一昨日の夜下痢1回、昨日の朝からは下痢が1日5回ほど続いています。
昨日病院でロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルスの検査は陰性で風邪もずっとひいてたし腸にきてるか胃腸風邪でしょうとのことだったのですが、
昨日の夜から今日の朝した下痢もロタウイルスのような黄色いモコモコ?っぽち下痢です。
胃腸風邪でもこのような下痢になるのでしょうか?
(病院に行くまでの下痢は黄色いでも濃い黄色の下痢で食べた物も混じってるような感じでした。)
整腸剤を処方してもらって昨日のお昼から飲んでます。
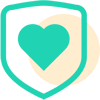
小さなお子さんの体調が不安定な時期は、親御さんとしてもとても心配になりますよね。
ご相談のような黄色くてモコモコした下痢ですが、胃腸風邪でもそういった便になることは十分にありえます。特に1歳半くらいのお子さんは、腸の働きがまだ未熟なため、ウイルス性の風邪が腸に影響を与えると、便の形や色が変わりやすくなります。ご指摘のようにロタウイルスの便に似ていても、検査で陰性だったのであれば、他のウイルスや細菌の影響による胃腸炎の可能性が考えられます。
また、保育園に通い始めたばかりの時期は、いろいろなウイルスに初めて接触することが多く、風邪や胃腸炎が頻繁に起こるのも決して珍しくありません。整腸剤で少しずつ腸内環境が整ってくると、便の状態も次第に落ち着いてくることが一般的です。
どうかご無理なさらず、少しでも安心して過ごせるようお子さんの様子をゆっくり見守ってあげてください。