整形外科で骨粗鬆症の薬を4年ほど飲み続けている母についての相談です。4年前に骨粗鬆症と診断されエルデカルシトールを飲んでいます。最近になり太ももから足首までの痺れを訴えスタスタ歩き回っていた母もヨタヨタ歩きになり長時間歩くのが困難になり、通ってる主治医に相談して脳のMRIの検査をしてもらったら異常はなし。運動不足なんじゃないかなぁと軽く言われウォーキングを少しづつしていたところ腰を痛めて断念。あまりにも痛かったというので接骨院に行き腰に電気?をかけてもらったらそこの接骨院の先生に『歩き方や話し方を見てるとパーキンソン病かもしれないから検査した方いいですよ、』と言われたらしく母が気にしてしまっています。そうこうしているうちに目眩を訴えて耳鼻科へ行き、耳鼻科の先生から目眩の薬を処方してもらい1ヶ月ほどで改善されたので耳鼻科へいくのをやめて、今朝もまた目眩を訴えて来ました。そこで質問です。整形外科へ通って四年経っていますが3ヶ月に一度血液検査、半年に一度レントゲン、脳のMRIは3ヶ月前に2年ぶりに撮りました。身体は4年前に比べたら2センチほど縮みました。接骨院の先生からパーキンソン病かもしれないと言われて気にしているのですが、脳のMRIをとった時にパーキンソン病は分からないものなのでしょうか?また、4年も整形外科に通っているのに悪化するのは、先生曰く運動不足なのでしょうか?歩くのがしんどそうで母が可哀想です。病院を変えるべきでしょうか。
骨粗鬆症の母、歩行困難とパーキンソン病の可能性?病院を変えるべきか
MRIではパーキンソン病はわかりません。
歩行状態の悪化原因については一度脳神経内科で診ていただいてはいかがでしょうか。
残念ながら、一般的なMRI検査ではパーキンソン病の発見は難しいと思います。
正常の脳とほとんど区別がつかないからです。
SPECTという特殊なMRI検査をすれば判別がつきますが、これはそれこそ、パーキンソン病を疑って医師がオーダーしないと健康保険が利かないのです。
(SPECTは脳卒中などでも健康保険が利きますが、でも脳卒中は一般的なMRI検査でわかるので、自己負担額が高くなるSPECTをわざわざオーダーするケースはあまりないと思います)
パーキンソン病の専門は神経内科になります。
整形外科は専門外となりますので、気になるのでしたらぜひ神経内科への受診をお勧めします。
なお骨粗鬆症の薬は、骨密度を劇的に改善するほどの強い効果があるわけではありません。
骨密度を劇的に改善するような強いお薬を作ったとしても、副作用で顎の骨が弱くなったり、逆に骨折が起こりやすくなる恐れがあるため、そのようなお薬は現状では開発しづらいのです。
ご高齢の方は年齢的に骨密度が下がる一方となりますので、骨密度の下がり方をなるべく抑えるためのお薬となります。
それゆえ、服薬期間はどうしても長くなりがちです。
「骨粗鬆症がなかなか治らないから整形外科医の腕が悪い」ということではありませんので、どうかその点はご理解ください。
仮に神経内科に通院することになったとしても、骨粗鬆症の治療は引き続き整形外科で行うのが一般的な対応だと思います。
接骨院の先生からパーキンソン病かもしれないと言われて
>接骨院の方は医師ではありませんので診断する能力はないと思われてください。
そのような医療関係者でないものの発言で不安に思うことはないです。
姿勢は骨粗鬆症があれば前かがみになりますし、それに伴って歩き方も変わります。
年齢がわかりませんが、毎日歩いていたとしても体は衰えていきます。
それは異常なことではなく、加齢に伴う生理的な老化で生きている以上避けられません。
風邪などを引いて急に動けなくなる病的老化を来さないことが重要となります。
パーキンソンであれば歩き方以外にも特徴的な症状もありますので流石に主治医も疑うのではないでしょうか。内服に関しては継続いただいて良いと思いますが、腰椎疾患なども考えられますので整形外科で腰椎周辺のMRIなどは評価いただけないかご相談いただいてみても良いかと思います。
MRIでは、わかりませんね。
お話からはフレイルと言われる状態かと思います。
骨粗鬆症は継続治療された方がいいです。
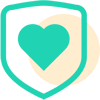
たしかにパーキンソン病では小刻み歩行等の症状が現れますが、お話を伺う限りでは、まだパーキンソン病とは言い切れないと思います。頭部MRIだけでは、パーンキンソン病かどうかはわかりません。歩行障害については頚椎疾患や腰椎疾患等の可能性も否定できないので、主治医の先生に相談してはいかがでしょうか。接骨院のスタッフの発言については医学的根拠はないので、あまり聞かない方が良いです。